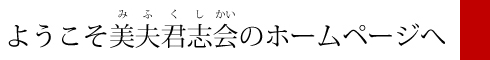会則・その他規約
美夫君志会 会則
◇ 本会は美夫君志会と称する。
◇ 本会は万葉集の研究、およびその普及を目的とする。
◇ 万葉集の研究者、愛好者は何人でも申し込みによって会員となることができる。
◇ 本会には会長・副会長・常任理事・理事をおく。
◇ 会長は必要に応じて総会を招集することができる。
◇ 本会は年2回万葉研究誌『美夫君志』を発行し、
年1回の大会と研究発表会をそれぞれ開催し、年10回の月例会を開催する。
◇ 本会は随時、万葉遺跡踏査、その他の事業を行なう。
◇ 本会は年1回の理事会を開催する。
◇ 会員は会費年額4000円(学生3500円)を前納する。
◇ 本会の目的に賛同する者から寄付金を受け取ることができる。
◇ 会員は万葉研究誌『美夫君志』に投稿し、大会その他本会の行事に
出席することができる。
◇ 役員(会長・副会長・常任理事・理事)の任期は3年(再任を妨げない)とする。
◇ 役員(会長・副会長・常任理事・理事)の定年は原則として満70歳とし、
定年に達した日の属する会計年度の末日をもってその職を退く。
◇ 本会には名誉会長・名誉会員を置くことができる。
◇ 本会の会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日におわる。
◇ 本会の事務は中京大学文学部内美夫君志会において行なう。
[改訂] 2018年3月11日
[施行] 2018年4月1日
投稿論文査読規約
(編集担当理事)
第一条 常任理事会は、常任理事の中から六名以上の編集担当理事を選出し、毎年、理事会の承認を得る。
二 編集担当理事は、雑誌『美夫君志』に投稿され、事務局が受理した論文(以下、当該論文と記す)の査読及び、雑誌『美夫君志』の編集にあたる。
三 常任理事会は、編集担当理事の中から、編集長一名と偶数名の編集委員を選出し、編集委員会を構成する。また、常任理事は、査読の公平性に照らして編集委員会の構成員について守秘義務を負う。
四 同一の編集担当理事は、連続する複数号の編集委員会の構成員となってはならない。ただし、やむを得ない事情が発生した場合は、この限りではない。
(編集委員会)
第二条 編集委員会は、査読、採否の決定、投稿者への結果通知、その他、雑誌『美夫君志』の編集に関わることを管掌する。
二 事務局は、当該論文を編集委員会に送付する。
三 当該論文の送付を受けた編集委員会は、当該論文が雑誌『美夫君志』掲載にふさわしい水準のものであるか否かを審査し、採否結果と査読意見を文書化する。編集委員は採否結果と査読意見を編集長に送付する。
四 編集長は、採否結果と査読意見を集約し、採否の原案を策定し、編集委員に送付する。
五 編集委員会は、協議の上、当該論文の採否結果を決定する。
六 編集長は、採否の概要を投稿者に通知する。この際、採否結果のA~Eを投稿者 に示す必要はない。
七 編集長は、査読状況を適宜常任理事会に報告する。
八 査読に際して、投稿者は匿名として扱う。
(採否結果)
第三条 採否結果は以下の五種類とする。
A:採用
表現等の微細な修正を求める場合もあるが、再査読せず掲載するもの。掲載可を通知する際、編集長がまとめた査読意見を付すことができる。
B:掲載前提の再審査
掲載を前提として部分的な修正や改稿を投稿者に求めるもの。採否結果を通知する際、編集長がまとめた査読意見を付す。
C:不採用(1)
投稿されたままでは掲載できないが、書き換えによって掲載可に至る可能性があるもの。採否結果を通知する際、編集長がまとめた査読意見を付し、再投稿を促す。
D:不採用(2)
不採用であり、かつ再投稿を促さないもの。採否結果を通知する際、編集長がまとめた査読意見を付すことができる。
E:不採用(3)
再投稿を受け付けないもの。この判定を下すには編集委員会の総意を必要とする。投稿者に不採用とともに再投稿を受け付けないことを通知する。編集長がまとめた査読意見は付さない。
(採否結果に対する不服申し立て)
第四条 投稿者より採否結果に対する不服申し立てがあった場合、A~D判定の投稿については編集委員会において再審査し、その結果を投稿者に通知する。ただし、再々審議は行わない。E判定の投稿については、編集長のまとめた査読意見とともに編集委員の総意がE判定であったことを通知し、再審議は行わない。
(再投稿)
第五条 当該論文の再投稿があった場合、初度の投稿時の編集委員会が担当する。ただし、編集担当理事の変更などがあった場合は、この限りではない。
二 B判定を受けた論文が再投稿された場合、編集委員会の過半数の掲載可の判断をもって掲載可とする。
三 C~D判定を受けた論文が再投稿された場合、編集長がまとめた初度時の査読意見を参考にすることができる。
三 複数回の再投稿を求める場合もある。
四 題名変更などにより再投稿か否かの判断が困難な場合、常任理事会において判断する。
(附則) この規約は2025年7月5日より施行する。
全国大会研究発表の採否決定規約
(資格)
第1条 研究発表申し込みのできる者は美夫君志会(以下、「本会」という。)会員に限る。研究発表は原則として1名で行うこととするが、複数名で行う場合、発表者の半数以上が本会会員であり、かつ、筆頭発表者は本会会員でなければならない。
(発表内容)
第2条 発表内容は、上代文学に関する学術的研究とし、未発表のものに限る。
(公示)
第3条 本会全国大会における研究発表の申し込みは、以下の文面を公表することをもって公示する。
美夫君志会全国大会における研究発表を希望される方は、下記「申し込み要領」に従って申し込んでください。
研究発表申し込み要領
1.発表内容
○上代文学に関する研究で未発表のもの。
2.申し込み方法など
○発表題目・800字以内の発表要旨・氏名・所属・住所、電話番号、メールアドレスを明記の上、学会事務局宛にメールにてお申し込みください。
○事務局に到着次第、受付の旨のメールを返送 しますので、4月7日までに連絡がない場合は、事務局にメールで問い合わせてください。
○締め切りは3月末日です。通常、4月末日までに採否の連絡をします。
○発表時間は30分、質疑応答は15分です。
3.採否
○採否は常任理事会に一任されます。
(採否の決定)
第4条 常任理事会は、3月末日までに本会事務局に到着した研究発表申し込みについて、以下の方法によって採否を決定する。
(1)本会事務局に提出された研究発表の要旨を精査し、総合的に判断して発表の許諾を審議する。その際、申込者(発表希望者)名は原則として匿名としたうえで審議を行う。
(2)常任理事会出席者による無記名投票をもって採否を決定する。
(3)採否にあたっては、賛成票の多い順に採択する。
(4)発表者数の上限は7名とする。
(5)反対票が投票総数の半数を超えた場合は、いかなる事情があっても採択しない。
(6)賛成票と反対票とが同数の場合、全発表者数が7名を超えない限り採択することとする。
(7)投票結果の最下位が同票数となり全発表者数が7名を越える場合は、再度審議の上、最下位者のみを対象に通常の方法で再度投票を行い、賛成票の多い順に採択する。この再度の投票によっても決しなかった場合は、最終判断を本会会長に委ねることとする。ただし、この場合も全発表者数が7名を超えることはない。
(採否の連絡)
第5条 本会事務局は、常任理事会終了後、速やかに研究発表申し込み者に採否結果を連絡する。その際、発表申し込み者には採否のみを連絡し、票数などそれ以外の情報は伝えることがない。
(採否情報の取り扱い)
第6条 研究発表申し込みにかかる投票結果は、本会事務局において3年間保存する。
(守秘義務)
第7条 常任理事は、票数などの採否情報に対して守秘義務を負う。
(開示)
第8条 研究発表に採択されなかった申し込み者当人より情報開示請求があった場合、当該請求者の投票結果のみを開示し、それ以外の情報を開示することはない。
(附則) この規約は2025年7月5日より施行する。